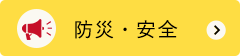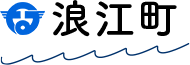本文
【2024年11月6日】 49年ぶり 浪江産の米を新嘗祭に献穀
令和6年11月6日
報道機関各位
福島県浪江町/49年ぶりに浪江産の米を新嘗祭に献穀します
令和6年新嘗祭に、49年ぶりに浪江産の米を献穀することとなり、10月21日天皇皇后両陛下御会釈のため、
献穀者が町長とともに皇居を訪問しました。(献穀者:半谷啓徳さん 37歳)
●御会釈を終えた感想
新嘗祭献穀は一生に一度と思い、引き受けました。天皇皇后両陛下への御会釈は、とても緊張しましたが、たいへん貴重な経験をさせていただいたと思います。今、農業者として米作りを継続していく責任を強く感じています。今回、新嘗祭の献穀をしたことが、浪江町の今後の農業の発展につながってほしいと思います。
●新嘗祭献穀の概要
献穀は、宮中の恒例行事の中で最も重要な儀式の一つである「新嘗祭」に、各都道府県の農家が新穀を献納するもので、明治25年以来、現在まで続いている伝統的な行事です。今年の献穀者は、福島県から2名が推薦され、掌典長より承知した旨の回答があり決定されました。献納式は行われないため、献穀米(5合)は、鏡石町の米(5合)とともに、県から宮内庁へ献納されました。
浪江町からの新嘗祭献穀は、昭和50年(苅宿地区)以来49年ぶり。新嘗祭は、11月23日に執り行われます。
浪江町の献穀者 半谷啓徳さん(はんがい よしのり) 37歳 精米「天のつぶ」 ※詳細情報あり
●浪江町の農業(震災による被害、復興状況)
浪江町は、震災と原発事故によって約6年間におよぶ全町避難を経験。町内の一部で避難指示が解除されて以来(2017年3月末)一丸となって復興に取り組んでいる。現在も居住人口は震災前の1割程度と厳しい状況にあるが、町は、再生可能エネルギーを活用した新たな町づくりを進めており、2020年11月「なみえ水素タウン構想」を発表。また、2024年住みたい田舎1位(「田舎暮らしの本」宝島社)に選ばれるなど、復興を加速させている。
町の主要産業だった農業は、長期避難による農地の荒廃、人口減少、生産者の高齢化などの課題を抱え、現在の水稲作付面積は、わずか約300ヘクタールであるものの、意欲ある営農者達によって年々増加を続けており、新たな特産品(玉ねぎ、トルコギキョウなど)も次々に生まれている。
今後、更なる農業の発展に向けて、現在整備中の大規模畜産施設との耕畜連携を目指している。
この度の新嘗祭献穀の名誉は、町の誇りであり、真摯に復興に取り組む生産者の方々の力になるものと期待しています。
【問合せ先】 浪江町役場 農林水産課 農政係 吉田 Tel:0240-34-0245
(別紙)献穀者 半谷啓徳さんについて
●就農6年目の若手
今年の新嘗祭の献穀者である浪江町酒田地区の生産者・半谷啓徳さん(37歳、いわき市に避難)は、就農6年目の若手農家です。令和元年、会社員を辞め家業である農業を継承しました。
就農のきっかけは、まだ原発事故の避難指示が解除されず、人が住めない状況の故郷で、田んぼの再生を信じ、ひたむきに米の栽培に取り組む父・好啓さんや、近所の方々の姿を見たことでした。
半谷さんの水田のある「酒田地区」は、平成26年から父・好啓さんが近所の方とともに米の実証栽培に取り組み、原発事故後、初めて町内で米の収穫が行われた場所です。長期にわたり使用されなかったため水路が荒廃、水田に水を引くことができず、田んぼ近くに井戸を掘って水源を確保するなど、実証栽培は苦労の連続でした。「田んぼを守り、米作りの再開に向けて頑張る地元の人や父親の姿を見たとき、自分も農業をやってもいいかなと思いました。」と半谷さんは当時を振り返ります。
半谷さんは会社員を辞めた後、県主催の新規就農プログラムで農業を学び、令和元年、本格的に酒田地区での米栽培をスタートしました。現在の栽培面積は10ヘクタールで、牛丼チェーン「吉野家」に直接出荷するなど、安定した生産を続けています。また、町内の酒蔵「鈴木酒造」の日本酒「磐城壽」にも、半谷さんが生産したコシヒカリが使われています。
米農家の誉である新嘗祭献穀に選ばれたことについて、半谷さんは「自分は、まだ就農6年目であり、自分でいいのか?という思いはありましたが、一生に一度しかないと思い、引き受ける決心をしました。献穀をしたことが、これからの浪江町の農業の発展につながってほしいと思います。」と話されています。
●これまでの経過
・献穀者の決定 令和6年4月
・新嘗祭田植え 令和6年5月25日(土曜日)
・新嘗祭収穫 令和6年9月24日(火曜日)
・新嘗祭献穀者御会釈 令和6年10月21日(月曜日)