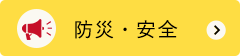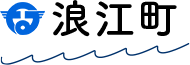本文
介護保険における住宅改修について
制度概要
介護保険の要介護認定で要介護・要支援と認定された方が、自宅において手すりの取り付けや段差の解消等の改修を行う場合、支給限度額を20万円として、利用者負担割合※(1割~3割)に応じて、かかった費用の9割~7割が介護保険の給付費として、保険者(浪江町)から払い戻されます。
※一定以上の所得がある方の利用者負担は、2割または3割となります。また、免除認定証をお持ちの方は利用者負担が免除となります。
工事着工前に、必ず事前申請が必要です。(事前申請せずに着工した工事は対象外です。)
対象となる工事
- 手すりの取り付け・段差や傾斜の解消(付帯する工事として転落防止柵の設置)
- 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
- 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
- 和式から洋式への便器の取り替え
- その他これらの各工事に付帯して町が必要な範囲と認める工事
手続きの流れ
(1) 担当のケアマネジャー等に相談(ケアマネジャー等が作成した理由書が必ず必要になります。)
(2) 住宅改修の内容について、事前に介護福祉課介護係へ相談
受領委任払い取扱事業者※に工事を依頼すると、利用者負担分を支払うだけで、工事をすることができます。(住宅改修工事は、登録事業者でなくても取扱いできます。)
※受領委任払い取扱事業者については介護福祉課介護係へお問い合わせください。
(3) 介護福祉課介護係へ住宅改修費の事前承認申請
工事着工前に事前申請が必要になります。
(4) 「住宅改修工事事前承認決定通知書」受け取り
(5) 施行・完成
(6) 住宅改修費の支給申請
事前申請に必要な書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修工事事前承認申請書 [Wordファイル/37KB] 〈記入例〉 [PDFファイル/155KB]
- 見積書(まとめて計上するのではなく部材ごとに記載してください。)
- 工事前写真(設置予定場所にライン等をご記載ください。)
- 平面図
- 理由書(福祉住環境コーディネーター※又はケアマネジャーが作成ください。)
※福祉住環境コーディネーターが作成した場合は資格証の写しを添付してください。
- 住宅名義人・住所が確認できる資料の写し(登記書や売買契約書等の日付、建物の住所、名義の分かる部分)
- 住宅改修承諾書 [Wordファイル/15KB](本人以外(親族等)の名義の場合に提出してください)
工事施工後に提出する書類
【受領委任払いの場合】
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修給付費受領委任払い支給申請書 [Wordファイル/36KB] 〈記入例〉 [PDFファイル/160KB]
- 工事後写真
- 受領書(原本:領収書や納品書でも可。工事完了日、工事費用額、本人の署名・押印が確認できるものを添付ください)
【償還払いの場合】
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 [Wordファイル/26KB] 〈記入例〉 [PDFファイル/245KB]
- 委任状 [Wordファイル/15KB](支払い口座が親族等、ご本人と異なる場合に必要です。)
- 工事後写真
- 領収書(原本:領収書宛名は本人又は委任状を提出した親族名でお願いします。返却希望の場合は原本確認後返却いたしますのでその旨を付箋等でご連絡ください。)
注意事項
- 新築住宅の改修工事は該当しません。
- 事前申請と事後申請の2段階による手続きが必要となりますが、事後申請が「正式な支給申請」となりますので、事前申請による見積額が必ずしも支給決定を意味するものではありません。
- 申請時に添付する改修前後の写真は比較が出来るように撮影してください。なお、付帯工事を行った場合はその写真も必要となります。
- 住民票所在地または避難先登録地以外の住所の住宅改修は認められません。
- 受領委任払いを行う場合、浪江町と施工業者で受領委任払いの契約を行っている必要があります。受領委任契約を希望される場合は介護保険課介護係までご連絡ください。