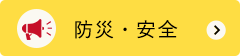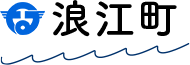本文
国民健康保険から受けられる給付(高額療養費・療養費・出産育児一時金・葬祭費)
1.高額療養費
国民健康保険に加入している方が、1か月(暦月ごと)に支払った医療費の一部負担金が下表の自己負担限度額を超えた場合、自己負担限度額を超えた額が、「高額療養費」として払い戻されます。
| 所得区分 |
自己負担限度額(月額) 3回目まで |
4回目以降(※3) | |
|---|---|---|---|
| ア | 所得(※1) 901万円超 |
252,600円 総医療費(10割の医療費)が842,000円を超えた場合は、 |
140,100円 |
| イ | 所得600万円超 から901万円以下 |
167,400円 総医療費(10割の医療費)が558,000円を超えた場合は、 |
93,000円 |
| ウ | 所得210万円超 から600万円以下 |
80,100円 総医療費(10割の医療費)が267,000円を超えた場合は、 |
44,400円 |
| エ | 所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
| オ | 住民税非課税世帯(※2) | 35,400円 | 24,600円 |
(※1)所得とは、世帯の国保被保険者の「基礎控除額後の総所得金額等」
(※2)住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯
(※3)過去12か月以内に、同一世帯内で高額療養費の支給が4回以上あった場合の限度額
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円 総医療費(10割の医療費)が842,000円を超えた場合は、 ※4回目以降は、140,100円 |
|
|
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円 総医療費(10割の医療費)が558,000円を超えた場合は、 ※4回目以降は、93,000円 |
|
|
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円 総医療費(10割の医療費)が267,000円を超えた場合は、 ※4回目以降は、44,400円 |
|
|
一般(課税所得145万円未満) |
18,000円 年間上限144,000円 |
57,600円 ※4回目以降は、44,400円 |
| 低所得者2(※4) | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1(※5) | 8,000円 | 15,000円 |
(※4)世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯
(※5)世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、かつ、各種収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯
自己負担限度額の計算について
・月の1日から末日まで、暦月ごとに計算します。月をまたいで入院(受診)された場合は、月ごとの計算となります
・同一の医療機関でも、入院・外来は別々に計算します
・食事療養費は対象外です
申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請書 [PDFファイル/140KB]
- 資格確認書等
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 該当月の領収書(原本)
- 世帯主名義の通帳
※郵送で申請する場合は、2・3および5の写しを同封してください。
※世帯主以外の方に振込みを希望される場合は、委任状 [PDFファイル/178KB]が必要です。
備考
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関へ提示することで、医療費の窓口の自己負担額が上表の限度額となったり、住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、入院時食事療養費等が減額されます。
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請はこちら
2.療養費
下表のような場合は、いったん費用を全額支払っても申請して審査で決定すれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。
※費用を支払った日の翌日から2年を経過すると、時効となり支給対象外となります。
※世帯主以外の方に振込みを希望される場合は、委任状 [PDFファイル/178KB]が必要です。
| 療養費の支給について | |
|---|---|
| こんなとき | 申請に必要なもの |
|
急病など、やむを得ない理由で資格確認書等を持たず治療を受け、医療費を10割支払ったとき ※医療機関等によっては、資格確認書等発行後に医療機関等窓口へ資格確認書等を提示すると、返金してもらえる場合があります。まずは医療機関等へお問い合わせください。 |
※郵送で申請する場合は、2・3および6の写しを同封してください。 ※申請から支給決定まで6か月程かかる場合があります。 |
| コルセットなどの補装具を購入したとき (医師が治療上必要と認めた場合) |
※郵送で申請する場合は、2・3および6の写しを同封してください。 |
| 国民健康保険加入後に、以前加入していた医療保険を使用して病院を受診し、医療費の返還を求められたとき ※以前加入していた医療保険の医療費返還後の手続きとなります。 |
|
3.出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産した場合、出産育児一時金として50万円(または48万8千円)を世帯主に支給します。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産された場合でも支給されます。
支給額
50万円・・・産科医療補償制度に加入している医療機関で22週以降出産したとき
48万8千円・・・産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産または妊娠12週以上22週未満の出産のとき
申請に必要なもの
直接支払制度を利用した場合 (出産費用が50万円または48万8千円未満の方)
- 出産育児一時金支給申請書 [PDFファイル/88KB]
- 資格確認書等
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 出産費用明細書(原本)
- 直接支払制度に関する同意書
- 世帯主名義の通帳
- 母子健康手帳(区市町村長の出生届出済証明印があるもの)
- 医師の証明書(死産・流産の場合)
※郵送で申請する場合は、2・3・5・6および7(または8)の写しを同封してください。
直接支払制度を利用しなかった場合
- 出産育児一時金支給申請書 [PDFファイル/88KB]
- 資格確認書等
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 出産費用明細書(原本)
- 直接支払制度不活用に関する書類
- 世帯主名義の通帳
- 母子健康手帳(区市町村長の出生届出済証明印があるもの)
- 医師の証明書(死産・流産の場合)
※郵送で申請する場合は、2・3・5・6および7(または8)の写しを同封してください。
※直接支払制度とは、保険者が直接医療機関に出産育児一時金を支払う制度です。
※申請できる期間は、出産日から2年間となります。
※世帯主以外の口座に振込みを希望される場合は、委任状 [PDFファイル/178KB]が必要です。
4.葬祭費
国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として、5万円を支給します。
申請に必要なもの
- 葬祭費支給申請書 [PDFファイル/70KB]
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 喪主の名義の通帳
- 葬祭が行われたことがわかるもの(会葬礼状等)
※郵送で申請する場合は、2・3および4の写しを同封してください。
※喪主以外の方に振込みを希望される場合は、委任状 [PDFファイル/178KB]が必要です。
※申請できる期間は、葬祭を行った日の翌日から2年間となります。