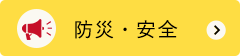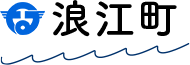本文
地域計画について(令和5年度から「人・農地プラン」の名称が「地域計画」に変更になりました。
浪江町の地域計画について
これまで地域の農業者により地域の農業、農地は守られてきました。
一方、農業者の高齢化や担い手の不足から不耕作農地の発生が全国的にも問題になっています。
これまで地域の農業者が守り発展させてきた地域の農業、農地を「将来にわたって地域の農地を誰が担っていくのか。」、「誰に農地を集積・集約化していくか。」などを地域の話し合いを通じ決めていくのが地域計画です。
一方、農業者の高齢化や担い手の不足から不耕作農地の発生が全国的にも問題になっています。
これまで地域の農業者が守り発展させてきた地域の農業、農地を「将来にわたって地域の農地を誰が担っていくのか。」、「誰に農地を集積・集約化していくか。」などを地域の話し合いを通じ決めていくのが地域計画です。
農林水産省 人・農地プランから地域計画へ<外部リンク>
具体的な取り組み内容
地域計画は令和6年度までに各地区で策定することが国で定められています。
浪江町の各地区でも地域計画の策定に向け、座談会などが開催されています。
策定に当たっては農林水産省から具体的な手順が示されています。
【策定までの具体的手順】
1 対象地区内の耕地面積の少なくとも過半について、農業者(耕作者、地権者)の年齢と後継者の有無等をアンケートで確認。
2 現況把握のアンケート結果を地図化し、5年~10年後に後継者がいない農地の面積を「見える化」し、地域での話合いの場で活用。
3 今後地域の中心となる経営体(中心経営体)への農地の集約化に関する将来方針の作成。
1,2を基に、農業者、自治体、農業委員会、JA、農地中間管理機構等の関係者が徹底した話合いを行い、5年~10年後の農地利用を担う経営体(中心経営体)の在り方を原則集落ごとに決めていきます。
浪江町の各地区でも地域計画の策定に向け、座談会などが開催されています。
策定に当たっては農林水産省から具体的な手順が示されています。
【策定までの具体的手順】
1 対象地区内の耕地面積の少なくとも過半について、農業者(耕作者、地権者)の年齢と後継者の有無等をアンケートで確認。
2 現況把握のアンケート結果を地図化し、5年~10年後に後継者がいない農地の面積を「見える化」し、地域での話合いの場で活用。
3 今後地域の中心となる経営体(中心経営体)への農地の集約化に関する将来方針の作成。
1,2を基に、農業者、自治体、農業委員会、JA、農地中間管理機構等の関係者が徹底した話合いを行い、5年~10年後の農地利用を担う経営体(中心経営体)の在り方を原則集落ごとに決めていきます。
農地中間管理機構(農地バンク)
農地中間管理機構は、平成26年度に全都道府県に設置され、農地を貸したい人と借りたい人を結びつける信頼できる農地の中間的受け皿の役割を担っています。
通称を「農地バンク」と呼び地域計画を進めていく上で農地の貸し借りを一括に担うことにより円滑な土地の貸し借りを推進しています。
浪江町役場内にも農地バンクから2人の地域コーディネータが常駐し地区の取り組みをサポートしています。
通称を「農地バンク」と呼び地域計画を進めていく上で農地の貸し借りを一括に担うことにより円滑な土地の貸し借りを推進しています。
浪江町役場内にも農地バンクから2人の地域コーディネータが常駐し地区の取り組みをサポートしています。
福島県農地中間管理機構<外部リンク>
各地区の状況
令和6年度までに地域計画の策定が求められていることから、各地区で策定に向けた話し合いが行われています。これら地区の取り組みに当たって浪江町、農業委員会、農地バンク、JAなどの関係機関が連携してサポートしています。(令和5年度から「人・農地プラン」は「地域計画」に名称が変更となりました。)
加倉地区
川添地区
苅宿地区
立野地区
酒田地区
西台地区
高瀬地区
樋渡・牛渡地区
小野田地区
幾世橋地区
北棚塩地区
南棚塩地区
田尻地区
藤橋地区
請戸地区
末森地区
室原地区
津島地区
令和5年度 農業担い手座談会(令和6年1月19日~20日開催)
令和6年1月に地域の担い手の方と今後の営農再開に向けた取り組みについて座談会(意見交換)を開催しました。
当日の県、JA等からの情報提供内容は資料をご参考ください。
当日の県、JA等からの情報提供内容は資料をご参考ください。
地域営農再開ビジョン
平成30年度に避難地域等における農業の将来展望を地域座談会等を通じ策定しました。
このビジョンを反映し営農再開に向けた取り組みを進めています。
このビジョンを反映し営農再開に向けた取り組みを進めています。
地域計画策定検討委員会
浪江町地域計画策定検討委員会設置要綱(令和2年7月13日告示第100号)に基づき設置された委員会で、集落・地域において、地域の中心となる経営体の確保や地域の中心となる経営体への農地集積を促すことにより、農業の競争力・体質強化を図り、持続可能な力強い農業構造を実現する地域計画を策定するため、地域計画の妥当性等の審査及び検討を行います。
第1回地域計画策定検討委員会(令和6年2月29日開催)
第2回地域計画策定検討委員会(令和6年3月28日開催)
令和6年度第1回 地域計画策定検討委員会(令和6年11月21日開催)
令和6年度第2回 地域計画策定検討委員会(令和7年2月25日開催)
確定した地域計画
令和6年4月15日決定
令和6年8月22日決定
令和6年12月6日決定
令和7年3月12日決定
地域計画の変更について
地域計画は一度作って終わりではなく、今後も見直しを行います。地域計画の変更は、次のように「定期更新」と「随時変更」とがあります。
定期更新
・年1回程度話し合いを行い、その結果をもとに地域計画の変更を行います。
・農業上の利用(地域の農業の将来のあり方・担い手・目標地図等の変更)に関する変更の場合は、基本的には定期更新の中でまとめて行います。ただし、随時変更の中の必要書類⑴地域計画変更申出書(様式第1号)については、届け出る必要があります。
・農業上の利用(地域の農業の将来のあり方・担い手・目標地図等の変更)に関する変更の場合は、基本的には定期更新の中でまとめて行います。ただし、随時変更の中の必要書類⑴地域計画変更申出書(様式第1号)については、届け出る必要があります。
随時変更
農業外利用や農地の位置、面積等の変更がある場合、地域計画の変更が必要です。
◆変更が必要な事項
・農業外利用(農地転用等に伴う地域計画区域つの変更等)
・区域の変更
・目標地図に位置付けられた担い手の削除、追加等
・担い手に位置付けられた農地の面積の変更、追加
・農業上の利用に関する変更で随時変更する必要がある場合
◆受付窓口
浪江町農林水産課
◆必要書類
⑴地域計画変更申出書
◆変更が必要な事項
・農業外利用(農地転用等に伴う地域計画区域つの変更等)
・区域の変更
・目標地図に位置付けられた担い手の削除、追加等
・担い手に位置付けられた農地の面積の変更、追加
・農業上の利用に関する変更で随時変更する必要がある場合
◆受付窓口
浪江町農林水産課
◆必要書類
⑴地域計画変更申出書
(2)添付書類
・登記事項証明書(原本)(受付日より3ヶ月以内に取得したもの。申し出により原本還付可)
・公図
・委任状(代理人が手続を行う場合)
・その他(事業計画の内容によっては、必要に応じて関係書類の提出を求める場合があります。
◆許可基準
次のすべてに該当すること。
(1) 地域計画に定める農用地の集積、集約化の方針に支障のないこと。
(2) 農地中間管理機構の活用方針に支障のないこと。
(3) 基盤整備事業への取組方針に支障のないこと。
(4) 多様な経営体の確保、育成の取組方針に支障のないこと。
(5) 農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針に支障のないこと。
(6) 農地転用を伴う場合は、既に設定されている利用権が解約されていること、または解約の見込みがあること。
・登記事項証明書(原本)(受付日より3ヶ月以内に取得したもの。申し出により原本還付可)
・公図
・委任状(代理人が手続を行う場合)
・その他(事業計画の内容によっては、必要に応じて関係書類の提出を求める場合があります。
◆許可基準
次のすべてに該当すること。
(1) 地域計画に定める農用地の集積、集約化の方針に支障のないこと。
(2) 農地中間管理機構の活用方針に支障のないこと。
(3) 基盤整備事業への取組方針に支障のないこと。
(4) 多様な経営体の確保、育成の取組方針に支障のないこと。
(5) 農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針に支障のないこと。
(6) 農地転用を伴う場合は、既に設定されている利用権が解約されていること、または解約の見込みがあること。
◆処理期間 申請を受理した日の翌月1日から起算して60日以内。なお、毎月20日を締切日として、変更手続きを行います。
◆令和7年11月受付の随時変更については、定期更新の変更手続き中であるため、地域計画変更申出書の受付はできません。
◆令和8年2月受付の随時変更については、手続きの見直中のため、地域計画変更申出書の受付についてはできません。皆様には、ご不便をおかけすることになりますが、ご理解とご協力をお願いします。
◆令和7年11月受付の随時変更については、定期更新の変更手続き中であるため、地域計画変更申出書の受付はできません。
◆令和8年2月受付の随時変更については、手続きの見直中のため、地域計画変更申出書の受付についてはできません。皆様には、ご不便をおかけすることになりますが、ご理解とご協力をお願いします。
なお、
(1)農地転用を伴う場合は農業委員会への申請前に地域計画を変更する必要があります。
(2)農地転用を伴う場合で、すでに福島県農業振興公社と貸し借りを行っている場合には、この賃貸借の解除が必要な場合があります。
◆受付窓口 浪江町農林水産課
◆必要書類
農地所有者 農地中間管理事業 賃貸借変更申出書
担い手 農地中間管理事業 賃貸借変更申出書
(1)農地転用を伴う場合は農業委員会への申請前に地域計画を変更する必要があります。
(2)農地転用を伴う場合で、すでに福島県農業振興公社と貸し借りを行っている場合には、この賃貸借の解除が必要な場合があります。
◆受付窓口 浪江町農林水産課
◆必要書類
農地所有者 農地中間管理事業 賃貸借変更申出書
担い手 農地中間管理事業 賃貸借変更申出書
地域計画の変更公告
令和7年7月3日変更
令和7年8月18日変更